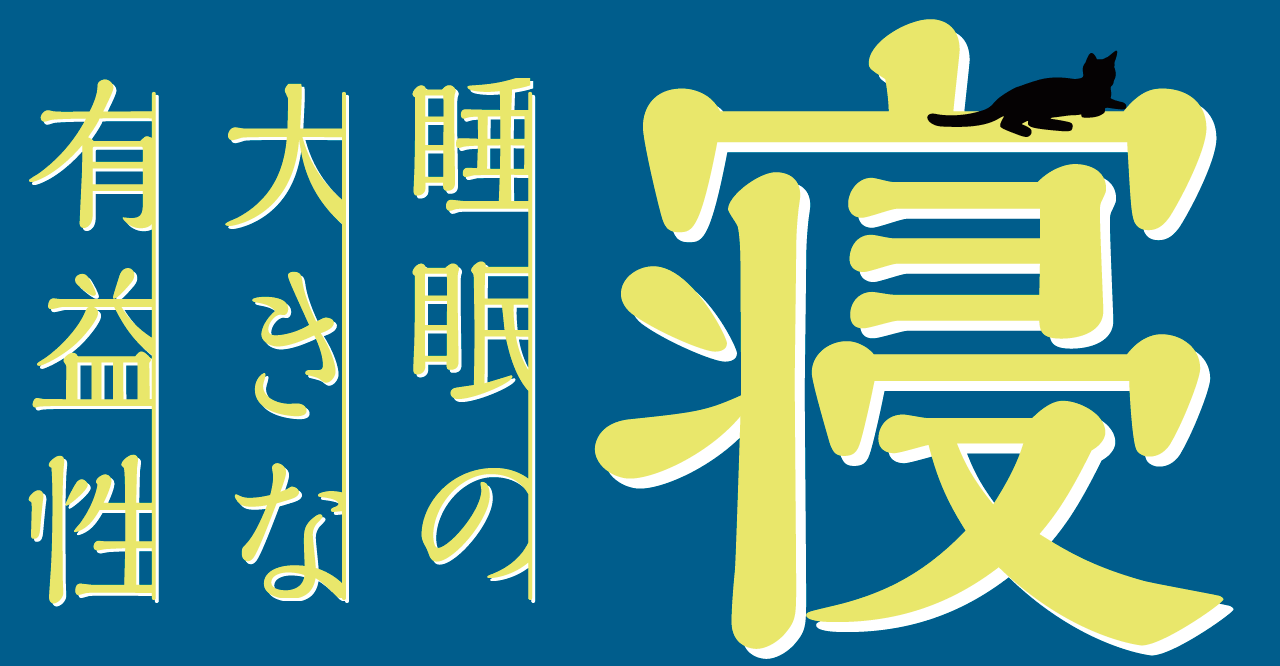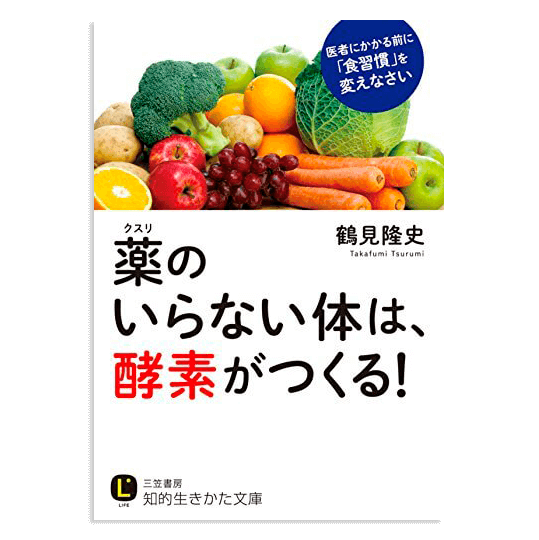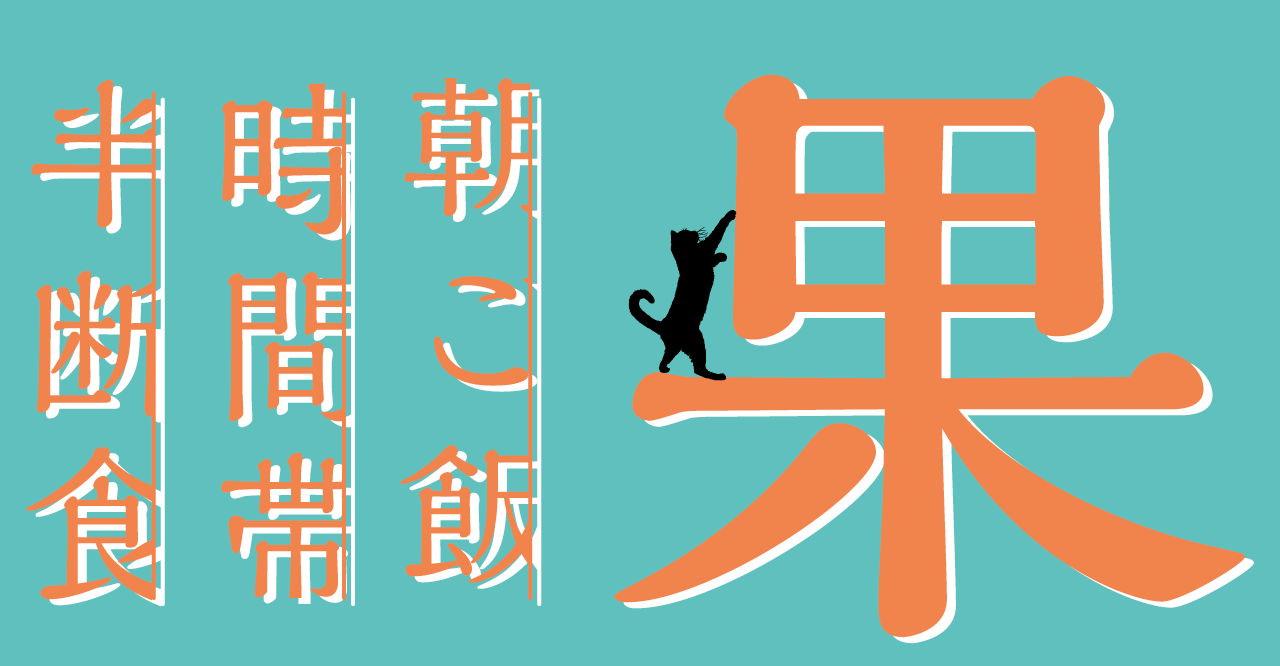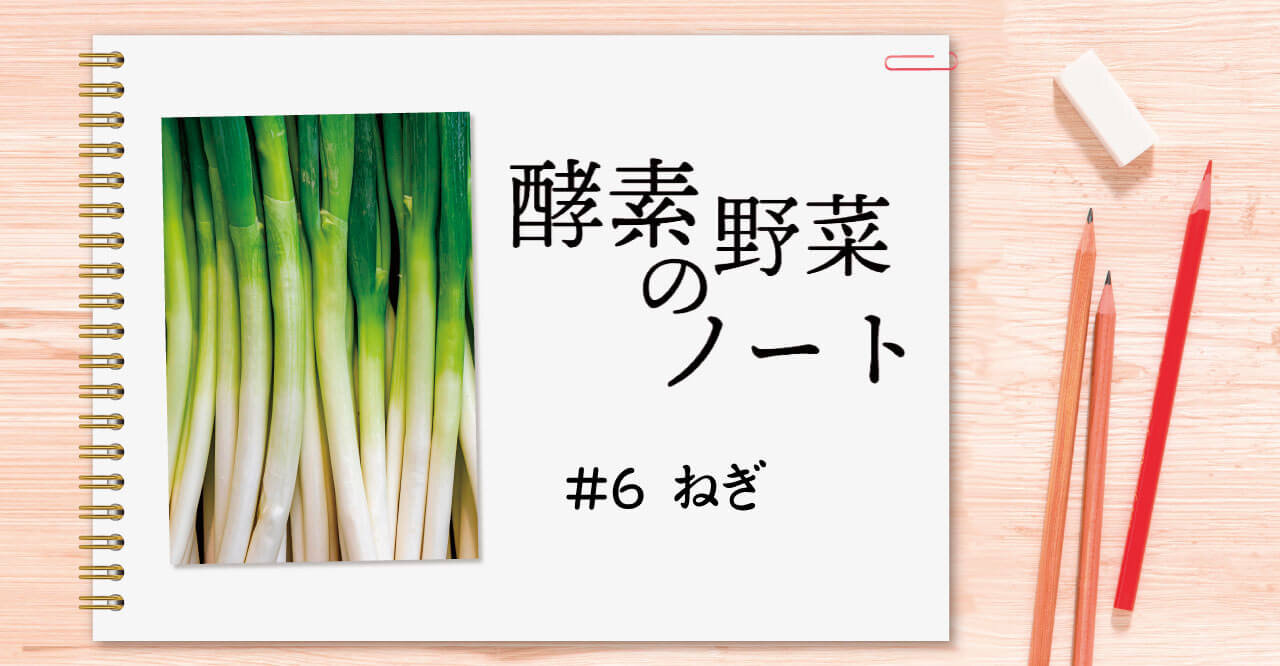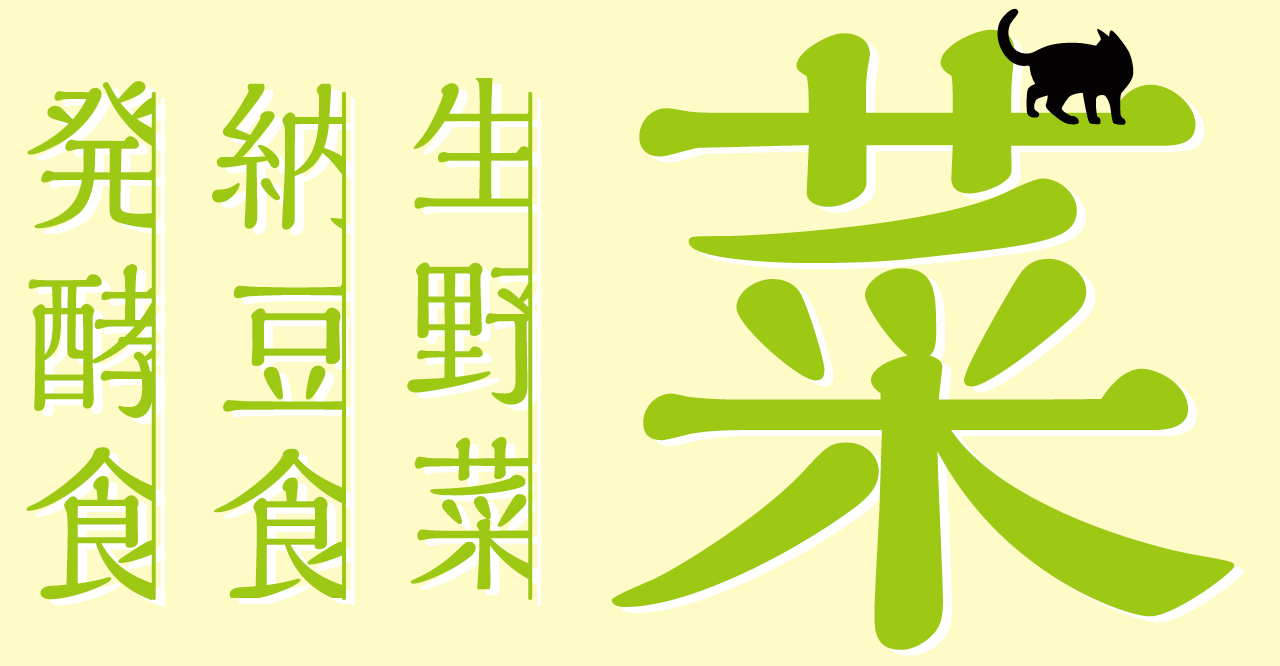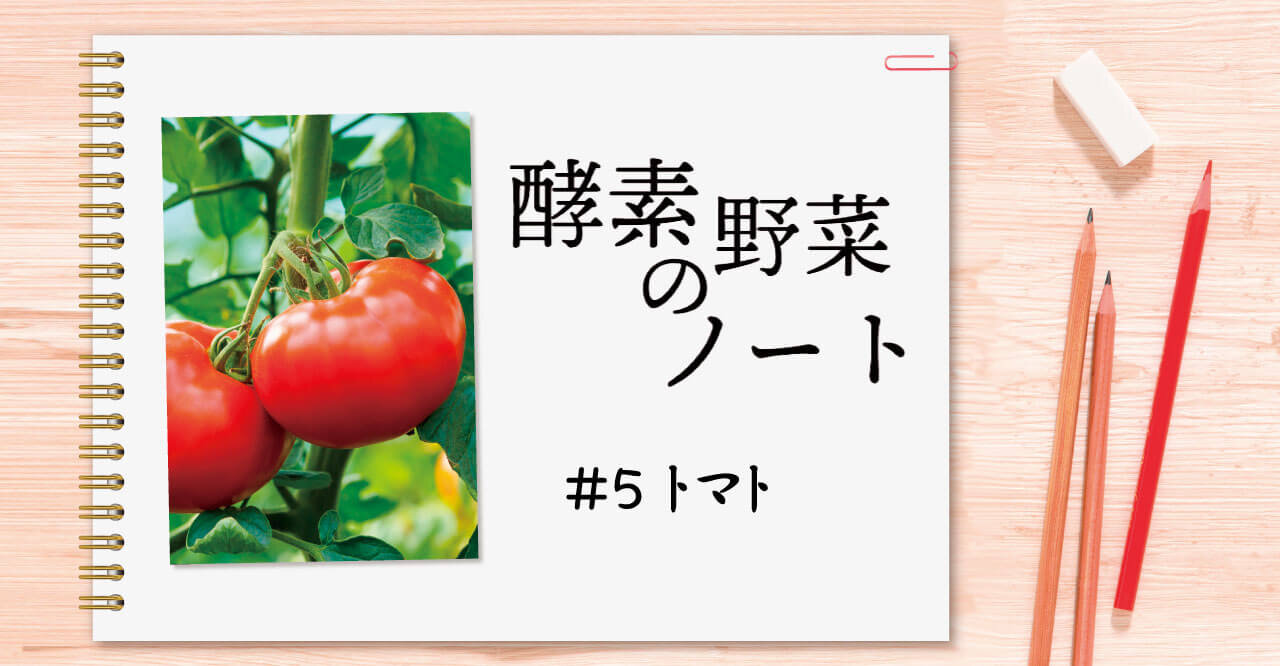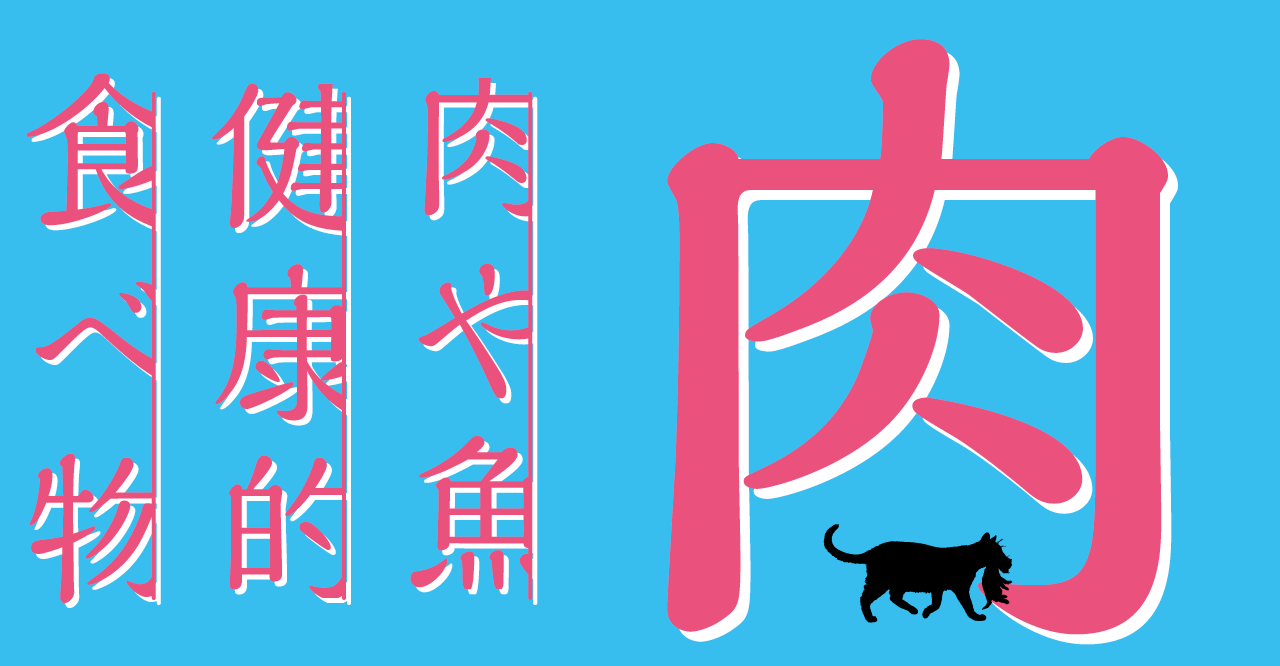酵素×睡眠
Summary
・快眠ホルモンを分泌させるには?
・良質な睡眠をとるためのポイント
※酵素×(カケル)は、日頃のライフスタイルと酵素の関係性について紹介していく特集です。主に鶴見隆史医師の著書より、生活に役立つ酵素に関係する情報を惜しみなく紹介してまいります。
健康や美容のために、人がもっとも大切にするべき習慣は「睡眠」と言っても過言ではありません。睡眠がなぜ心身のはたらきをキープすることに欠かせないのか?その秘密に科学的に迫ると、その一つに酵素のはたらきの正常化があるとも言えます。
どうか、最後までお読みいただき、体の中から未来をつくることにお役立てください。
※以下の書籍より引用、紹介
鶴見隆史(2005)薬のいらない体は、酵素がつくる!
医者にかかる前に「食習慣」を変えなさい pp.174~
(知的生きかた文庫:三笠書房)
快眠ホルモンを分泌させるには
最近、ちゃんと眠れていますか?
健康にとって睡眠が非常に大切であることは言うまでもないでしょう。でも、なぜ睡眠が大事なのか、ちゃんと理解されている方は少ないかもしれません。
睡眠の役割は、頭と体を休めるだけではありません。眠っているあいだには命と健康を保っていくための、さまざまな代謝活動が行なわれているのです。
まずは、体中の細胞や組織の点検・補修があげられます。傷んでいるところを元どおりにしたり、新しい細胞に入れ替えたりということですね。さまざまなホルモンがつくられるのも、ヘルパーT細胞やNK細胞などの免疫細胞が盛んに仕事をするのも睡眠中です。そしてなにより、翌日の消化や代謝に使われる体内酵素がチャージ(補充)されているのです。
つまり、きちんと眠らないと、新陳代謝がとどこおり、免疫力も弱まるうえに、酵素も足りなくなって、病気になりやすい体になってしまうのです。
これらの作業を十分に行なうためには、7~8時間は眠りたいところです。睡眠ホルモンであるメラトニンは、夜になると増えていき、深夜にかけて分泌量がピークを迎え、明け方にかけて減っていきます。また、8時間寝ればいいというわけではありません。同じ8時間でも、午後11時から朝7時まで眠るのと、午前4時からお昼まで眠るのとでは、睡眠の質がまったく異なってくるのです。
良質な睡眠をとるためのポイント
良質な睡眠をとるには次のようなことが大切です。
・遅くまで仕事をしない
眠りは、心と体をリラックスさせる副交感神経が優位にならないと訪れません。遅くまで仕事をしていては、仕事モードの交感神経から副交感神経への切り替えがうまくいきません。
・夜はパソコンやメールを見るのをひかえる
ハソコンやスマートフォンなどの強い光は、交感神経を刺激して、体を眠りから遠ざけてしまいます。
・午前0時前には布団に入る
人間本来の生理リズムに合わせて眠ることで、睡眠の効果が高まります。
・食べすぎや、遅い時間の食事を避ける
胃腸を休めて消化酵素の働きを抑え、その分を代謝酵素にまわすことで体のメンテナンスがしっかり行えます。また、眠るためにお酒を飲むのはおすすめできません。アルコールを飲みすぎると、一度は眠っても途中で目が覚めてしまい、レム睡眠 (浅い睡眠) とノンレム睡眠 (深い睡眠) のリズムが乱れて睡眠の質が低下します。
・午前中にウォーキングをする
・オリゴ糖や食物繊維、生食を増やし、腸内を乳酸菌だらけにして、セロトニン(メラトニンの原料)を活性化する
よく眠るには、生野菜、果物、発酵食品などから酵素をたっぷりと摂ることです。眠りをもたらすメラトニンは、セロトニンというホルモンからつくられますが、セロトニンを増やしてくれるのは腸内の善玉菌だからです。酵素食で善玉菌が元気になると、メラトニンの働きが高まります。睡眠は健康な生活の柱であり、自然な眠りに導いてくれるのもまた酵素なのです。
鶴見隆史医師について
医療法人社団森愛会理事長鶴見クリニック院長。1948年石川県生まれ。金沢医科大学医学部卒業後、浜松医科大学にて研修勤務。東洋医学、鍼灸、筋診断法、食養生などを研究。西洋医学と東洋医学を融合させた医療を実践。
病気の大きな原因は「食生活」にあるとして、酵素栄養学に基づくファスティングや機能性食品をミックスさせた独自の医療で、がんや難病・慢性病の治療に取り組み、多くの患者の命を救う。
3~5時間かけ問診や検査・処置を行うため患者数は1日数人に限定。酵素栄養学に基づいたファスティングメニュー(半断食)の提案だけではなく、ホルミシス(微量放射線)を発する玉川鉱石ドーム、ホルミシスサウナ、ゼロ磁場音響チェアでの物理療法。その他、水素点滴やPRA検査、そして、独自に開発し質を高め続けているサプリメントの処方。これらの治療により末期がんや難病に対しても大きな改善をもたらしており、その治療を求める声は国内にとどまらない。
執筆活動も精力的に行い、治癒症例、栄養学、ダイエットレシピなど、そのジャンルは多岐に及ぶ。特に酵素栄養学に関する本は第一人者の著書としてロングセラーとなっている。