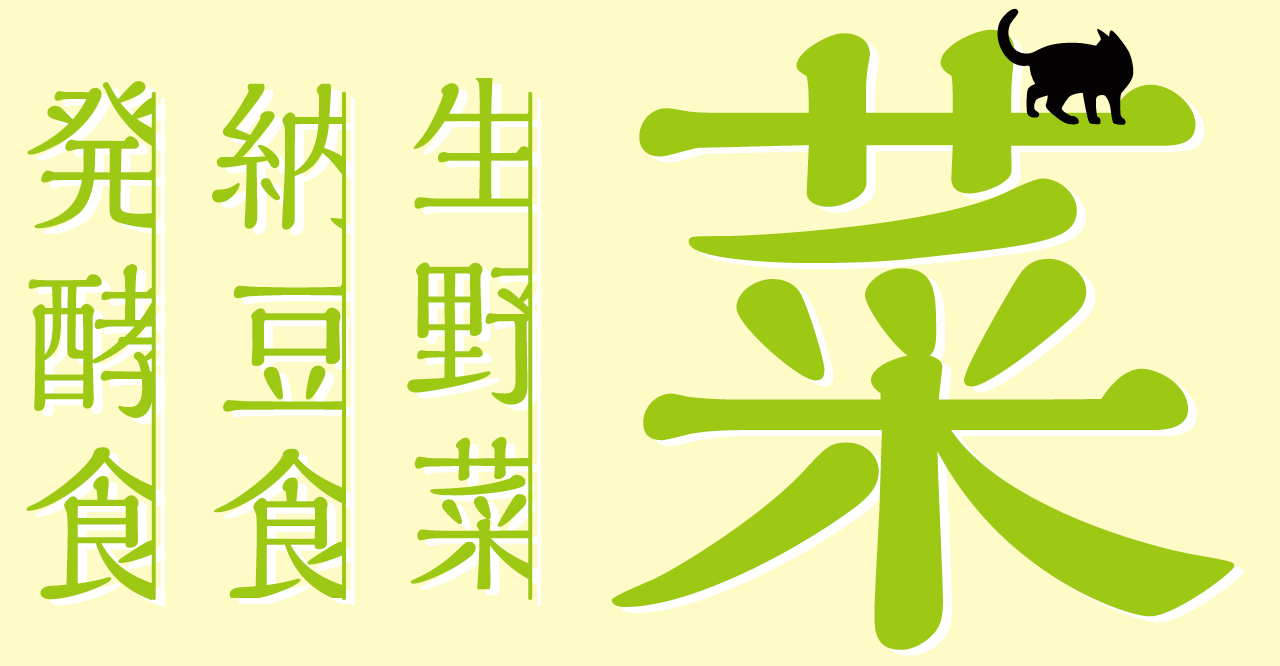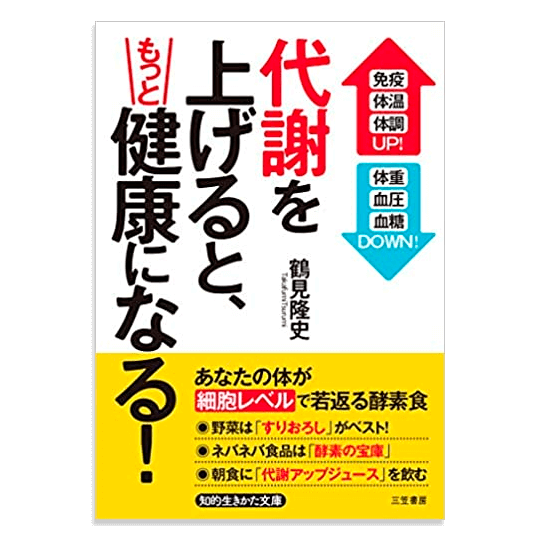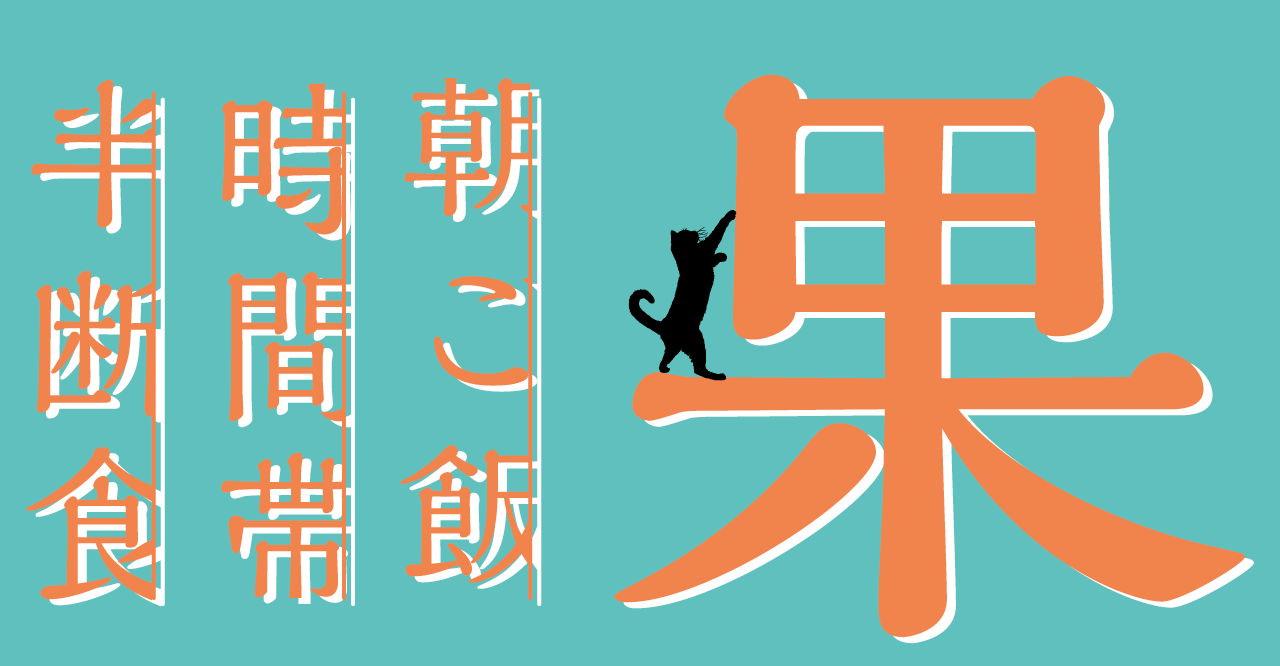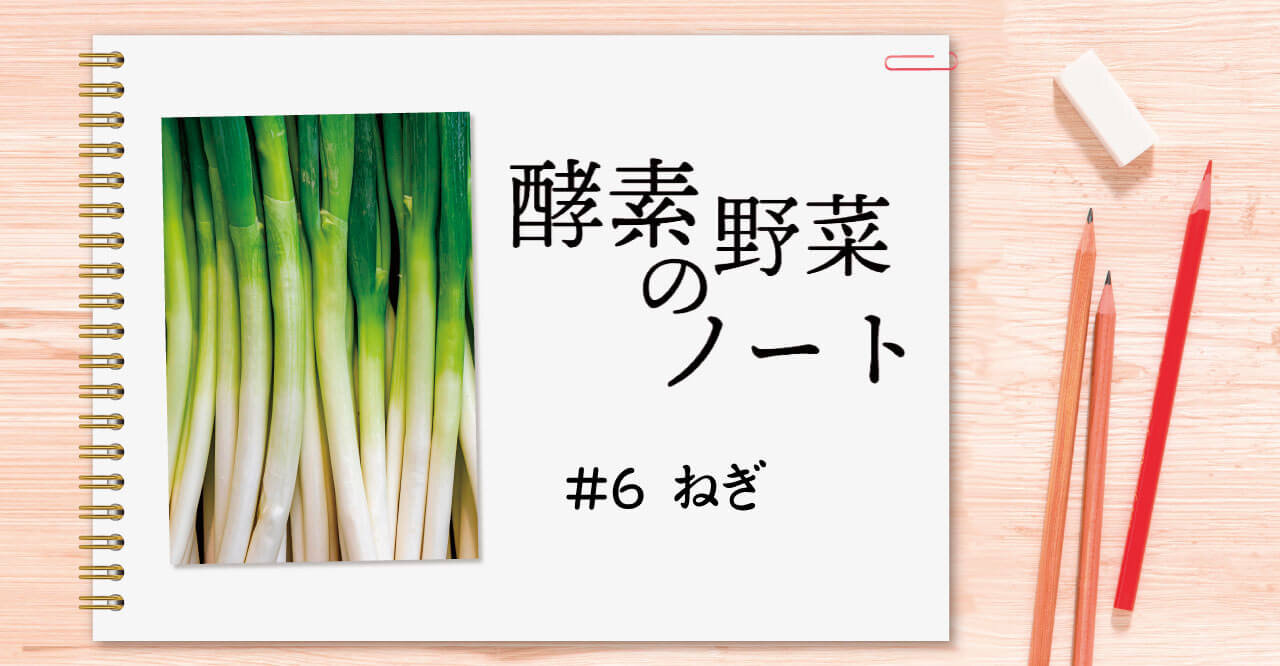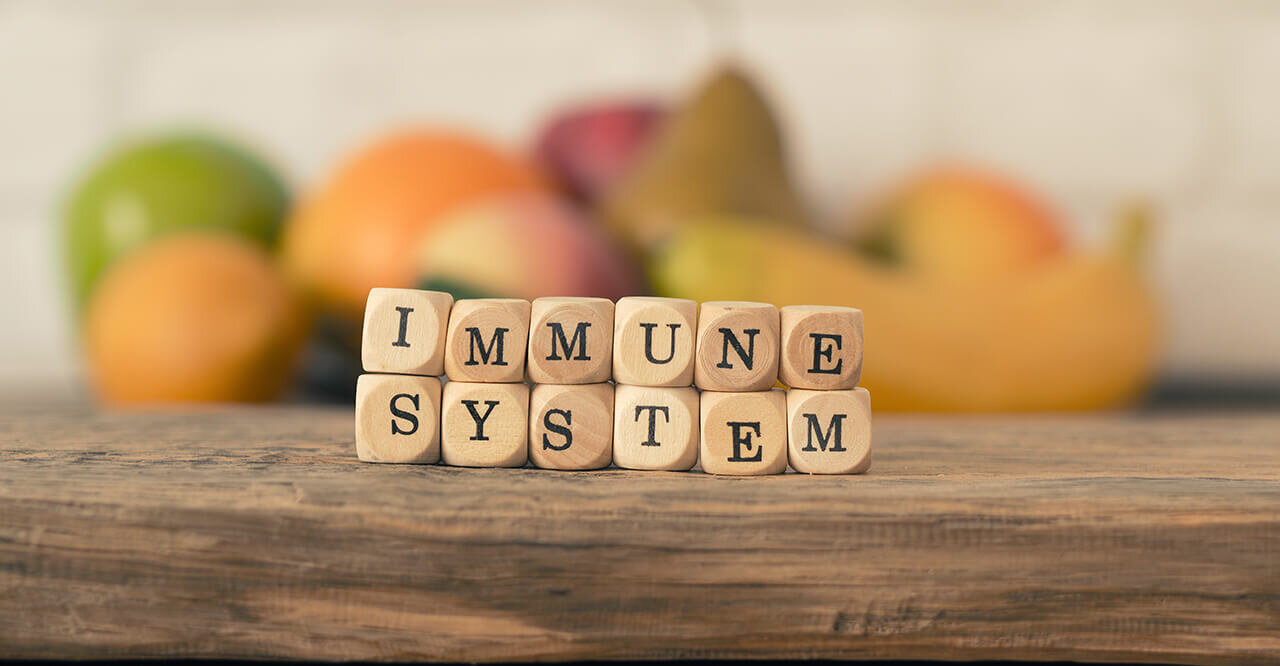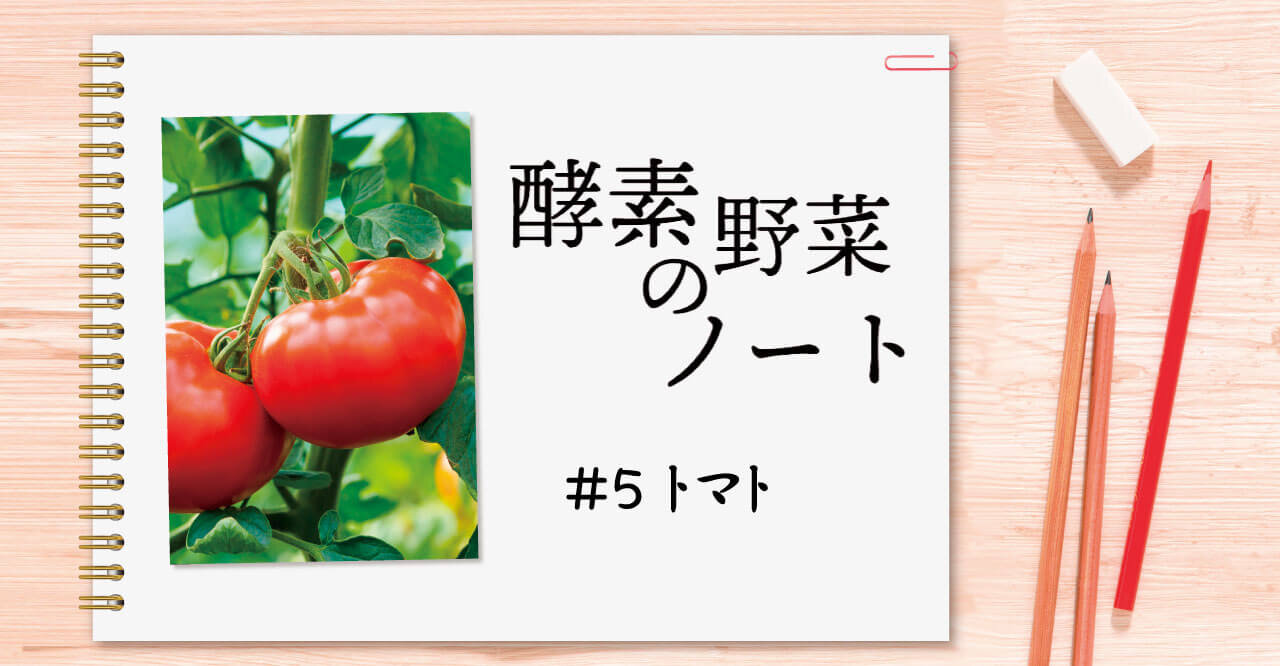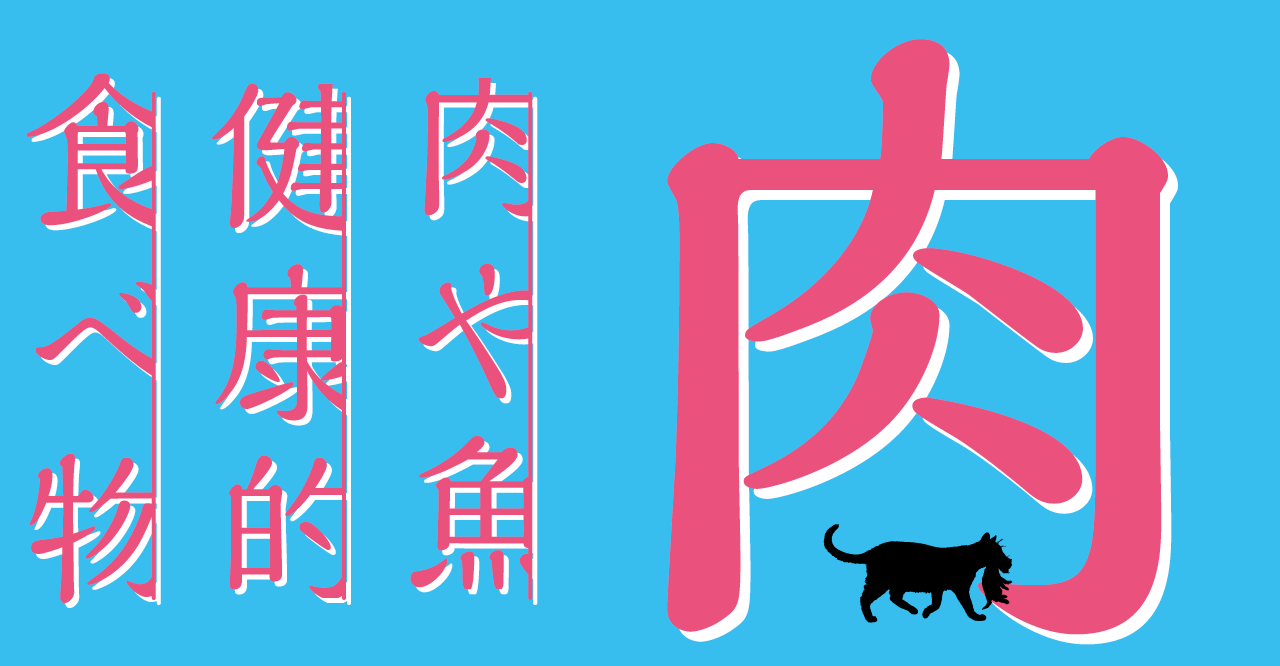酵素×野菜 = 生野菜は体を冷やすどころか体温を上げる
Summary
※酵素カケルは、日頃のライフスタイルと酵素の関係性について紹介していく特集です。主に鶴見隆史医師の著書より、生活に役立つ酵素に関係する情報を惜しみなく紹介してまいります。
生野菜を食べると体が冷える印象がありませんか?一時的に体温が下がり代謝が落ちているのではと思ってしまう人も多いかもしれませんが、生野菜を食べた方が血液がサラサラになり代謝が良くなります。
その他にも納豆や味噌などを食べることで腸活に繋がり、消化・吸収・エネルギー生産・排せつという代謝のプロセスがスムーズになります。
今回の酵素カケルは、代謝がテーマ。
どうか、最後までお読みいただき、体の中から未来をつくることにお役立てください。
※以下の書籍より引用、紹介
鶴見隆史(2018)代謝を上げると、もっと健康になる!
あなたの体が細胞レベルで若返る酵素食 pp.104~107
(知的生きかた文庫:三笠書房)
毎朝、納豆を食べるだけで腸が元気になる
たんばく質は人体に必要な栄養素なのに、困ったところがあります。これまで述べてきたように、消化が悪いのです。消化酵素をたくさん必要とするので、代謝酵素の働きにまで悪影響が出てしまいます。ただし、それは動物性たんばく質の場合。じつは、消化・吸収がスムーズで、酵素もむだ使いしない、魔法のようなたんばく質があるのです。それが、大豆たんぱく質。味噌や納豆、豆腐といった大豆を発酵させた食べ物に含まれるたんばく質です。
とくに、納豆は腸の大好物。腸内の善玉菌を増やし、悪玉菌を少なくする作用があります。善玉菌が豊富で活発だと、腸内環境は正常に保たれ、消化・吸収・エネルギー生産・排せつという代謝のプロセスがスムーズになります。
また、納豆には、血液をきれいにする「血栓溶解酵素」のナットウキナーゼが含まれていて、脳梗塞や心筋梗塞の予防になります。ほかにも、倉敷芸術大学の須見洋行教授の研究によれば、「病原体溶解酵素」あるリゾチームも含まれていて、強い抗菌作用があります。
そのほか、病気予防に欠かせないコリン、ビタミンK、レシチン、ジビコリン酸、イソフラボンも豊富に含まれています。納豆は病気予防・老化予防に必要な栄養素がたつぶり含まれているので、食卓に常備したい食品です。
ちなみに、納豆の持つネバネバ成分は、酵素の量と比例関係にあります。よく混ぜたネバネバした納豆を食べると、体内の代謝酵素も活性化されます。
なお、ワーファリン (抗凝血剤)を服用している方は、納豆を食べるのはNG。納豆に豊富なビタミンKがワーファリンの効用を弱めてしまうからです。ワーファリンは血栓ができることを予防する薬です。じつは、ワーファリンを使わずとも、納豆を使えば血液はサラサラになっていきます。納豆には、メナキノン7という特別なビタミンKが含まれていることが発見されました。メナキノン7は、ワーファリンに優るとも劣らない特別な血栓溶解ビタミンです。
毎朝納豆を食べれば、薬に頼らずとも血液をサラサラにすることができるのです。
納豆は「よくかき混せる」のがポイント!
生野菜は体を冷やすどころか体温を上げる
生野菜は生きた酵素を多く含み、私たちの代謝を上げるのに欠かせません。一方で、こんな説もあります。「生野菜ばかり食べていると、体が冷える」という説です。
たしかに私たちの体は、温かいものを食べると温まり、冷たい飲み物を摂ると冷えます。冷たい生野菜を食べると、体が冷えて、代謝が下がる印象を持つかもしれません。
しかし、生野菜を食べたとき、なんとなく体が冷えたように感じるのは、一時的なもの。生野菜を食べる習慣を続けていると、いずれ血液がサラサラになり、血流がよくなることで、体が温まってきます。最初の冷えがどうしても気になる方は、湯船によく浸かるなど、体を温める習慣も並行して行なってください。
生野菜が体の冷えを招くのではなく、体内の酵素不足が冷えを招くのです。ただ、生野菜ばかり食べるのも億劫な話。生野菜を食べる習慣を続けるコツは、食べ方にバラエティーを持たせることです。すりおろしたり、漬けたり、酢の物にしたり、ジュースにしたり、キムチやピクルスにしたり......。生野菜の食べ方はたくさんあります。たまにはゆでたり、蒸したり、煮たりして温野菜にして食べてください。野菜のかさが減るので、量をたくさん食べられるというメリットがあります。
また、加熱調理すると、栄養価がアップしたり、消化がよくなったりする野菜もあります。たとえば、ニンジンは、生よりもゆでたり炒めたりしたほうが、栄養の吸収がよくなります。キノコ類やイモ類も、加熱調理したほうが消化はよくなります。ただし、炒めると糖化してしまうデメリットもあるので注意が必要。ベストは炒め物は少なくすることです。
また、生の豆類には 「酵素抑制物質」 が含まれるため、加熱するのが基本。
野菜は煮ると、普通に咀嚼しただけでは壊れない野菜の細胞膜が破壊され、栄養成分の吸収がよくなります。加熱調理した野菜は酵素の働きの面では劣りますが、たくさんのメリットがあります。生野菜だけでなく、温野菜もどんどん毎日のメニューに取り人れましよう。
代謝を上げるには、とにかく1日の野菜の摂取量を増やすことです。無理に生野菜にこだわらず、自分の食べやすい方法で野菜を積極的に摂るようにしてください。
生野菜は毎食、サラダやすりおろしで食べるようにする。昼食やタ食では、煮たり炒めたりした野菜をプラスする摂り方をすれば、無理なく野菜をたつぶり摂れる食習慣になります。生と加熱調理した野菜を食べる目安としては、おおよその見た目で半分以上を生野菜、半分に少し欠けるくらいを加熱調理した野菜としましょう。
「生野菜6割」「温野菜4割」が目安!
鶴見隆史医師について
医療法人社団森愛会理事長鶴見クリニック院長。1948年石川県生まれ。金沢医科大学医学部卒業後、浜松医科大学にて研修勤務。東洋医学、鍼灸、筋診断法、食養生などを研究。西洋医学と東洋医学を融合させた医療を実践。
病気の大きな原因は「食生活」にあるとして、酵素栄養学に基づくファスティングや機能性食品をミックスさせた独自の医療で、がんや難病・慢性病の治療に取り組み、多くの患者の命を救う。
3~5時間かけ問診や検査・処置を行うため患者数は1日数人に限定。酵素栄養学に基づいたファスティングメニュー(半断食)の提案だけではなく、ホルミシス(微量放射線)を発する玉川鉱石ドーム、ホルミシスサウナ、ゼロ磁場音響チェアでの物理療法。その他、水素点滴やPRA検査、そして、独自に開発し質を高め続けているサプリメントの処方。これらの治療により末期がんや難病に対しても大きな改善をもたらしており、その治療を求める声は国内にとどまらない。
執筆活動も精力的に行い、治癒症例、栄養学、ダイエットレシピなど、そのジャンルは多岐に及ぶ。特に酵素栄養学に関する本は第一人者の著書としてロングセラーとなっている。