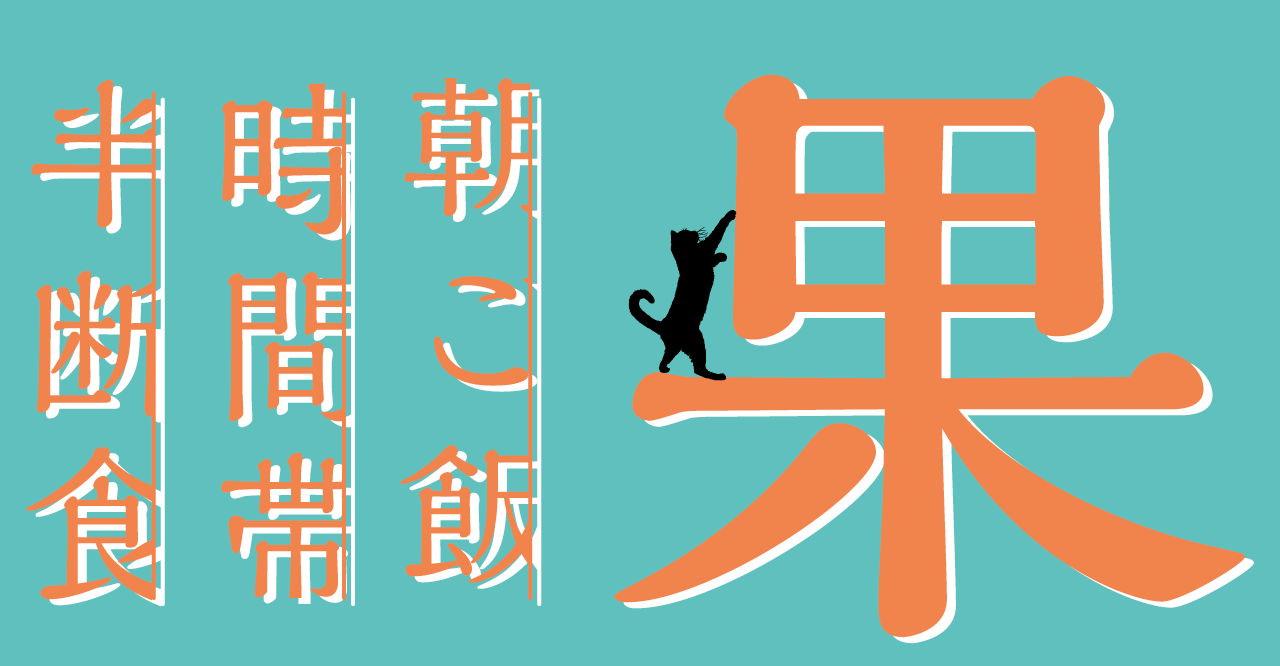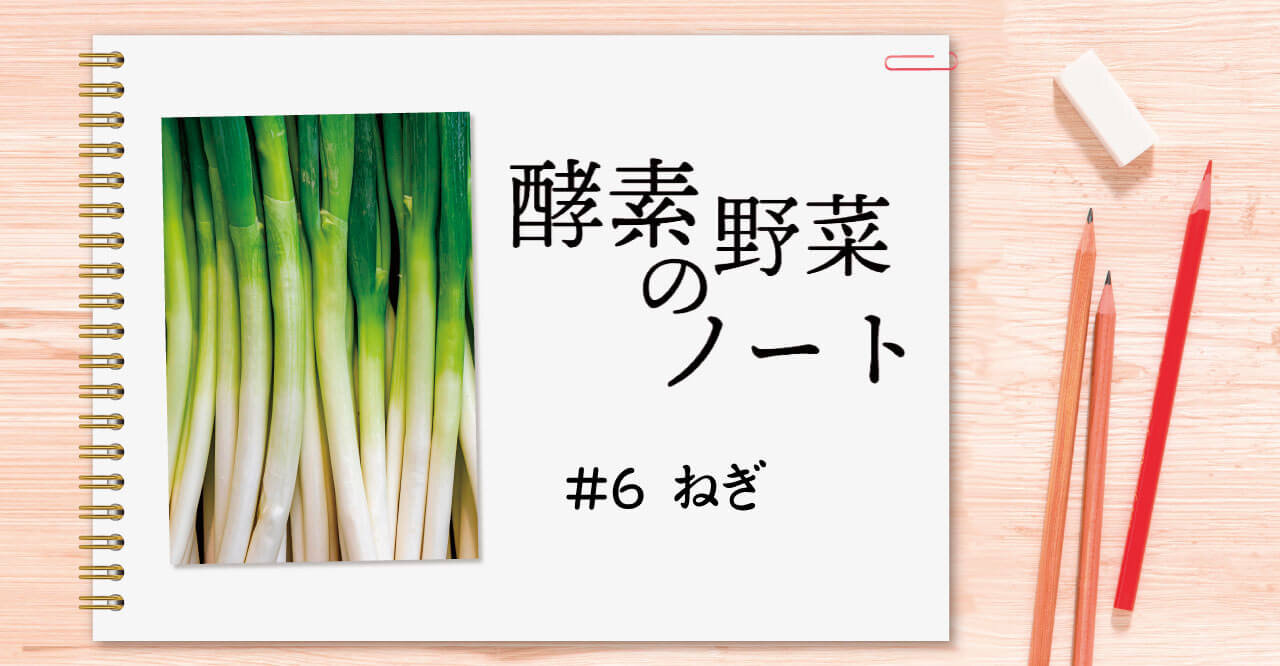唐辛子料理で体を温め、冷え性改善!
熱帯アメリカ原産の唐辛子は、辛味種にはタカノツメ、干し唐辛子、ヤツブサなどがあり、甘味種にはピーマンがある。また、シシトウや満願寺唐辛子というのは日本の在来種で、甘味種の唐辛子になります。ビタミンCやカロテンを多く含み、無機成分の鉄、マグネシウム、カルシウム、ナトリウム、カリウムなども豊富で、種子部分には、カルシウムとカリウムが非常に多いことがわかっています。
昔から唐辛子は香辛料、食用だけでなく、薬用としても用いられ、漢方では、肺炎、リウマチ、神経痛、筋肉痛などの皮膚刺激剤として使用するほか、消化不良の治療に使われています。また、凍傷(しもやけ)などの予防や、塗擦薬としても用いられています。このような効果をもたらす元は、唐辛子の辛味成分である「カプサイシン」であることが研究で解っています。
体を温め、血行促進
全身くまなく血管が張り巡らされ、血液が流れています。血液が細胞に必要な酸素と栄養素を供給すると同時に、不要な老廃物の排出をおこなっております。
ところが現代の暮らしには、大気や水の汚染、残留農薬等に汚染された食品、各種薬物による"ケミカルストレス"などといった、血液成分に変化をもたらす要因がたくさんあり、さらに、食事内容の西洋化にともなう脂肪分の増加や長期にわたる偏食によって、血液の収縮により血行が悪くなり、末端まで流れにくくなってしまい血行障害を起こします。細胞への酸素や栄養素が不足に陥り、いろいろな病気の元凶になるので、血液は常にきれいにサラサラで、血行が順調であることと、体を温めることが大切です。
健康な人にとって一定の体温とは、36.5度前後のことを言いますが、体温が低すぎたり、冷え性などのように体温が低い状態が続くと、消化・吸収力の低下、ホルモンや自律神経の変調など、全身に生理作用が低下して、腰痛、頭痛などのほか下痢、めまい、立ちくらみなどが起こりやすくなります。東洋医学では、冷えは、体のうっ血状態(血が異常に集まる)を招き、血の巡りを悪くし、細胞の機能の低下や、さまざまな病気の原因になると考えられています。
今の若者は昔に比べ基礎体温が低い傾向にあるとの統計も出ており、心配されています。
しかし、血行障害や体の冷えは、さまざまな病気の下地になり得るが、カプサイシンには体を温め、末梢血管の血行をよくし、全身の生体機能を活性化してくれる働きがあるので、食事をすると、夏には汗が吹き出たり、寒い冬には体が温まってくるが、これは食後、体熱産生が活発になるため、辛味成分であるカプサイシンは大いに役立っていると考えられています。
唐辛子の入った辛い料理を食べるとドッと汗が出るのも、体温を上げ、血行をよくするカプサイシンの作用の一つになります。度を過ぎたいわゆる、"激辛"ではなく、適度な辛みの香辛料は食欲増進のほかにも体を温めるのに役立ちます。