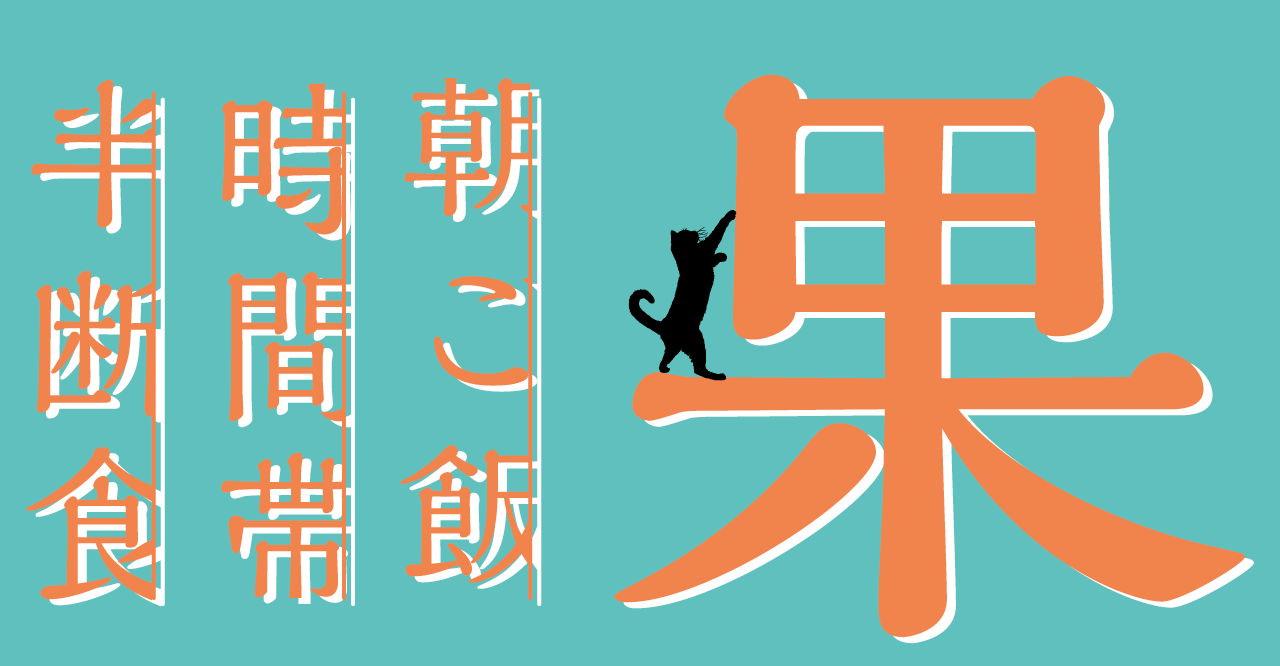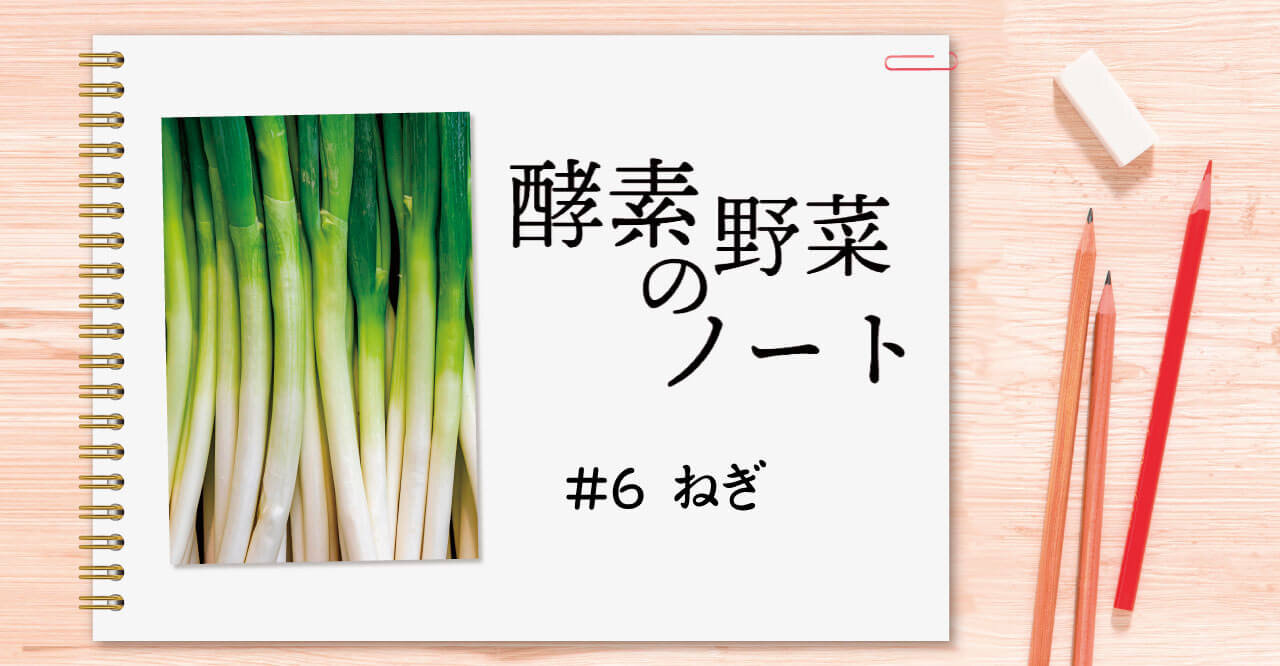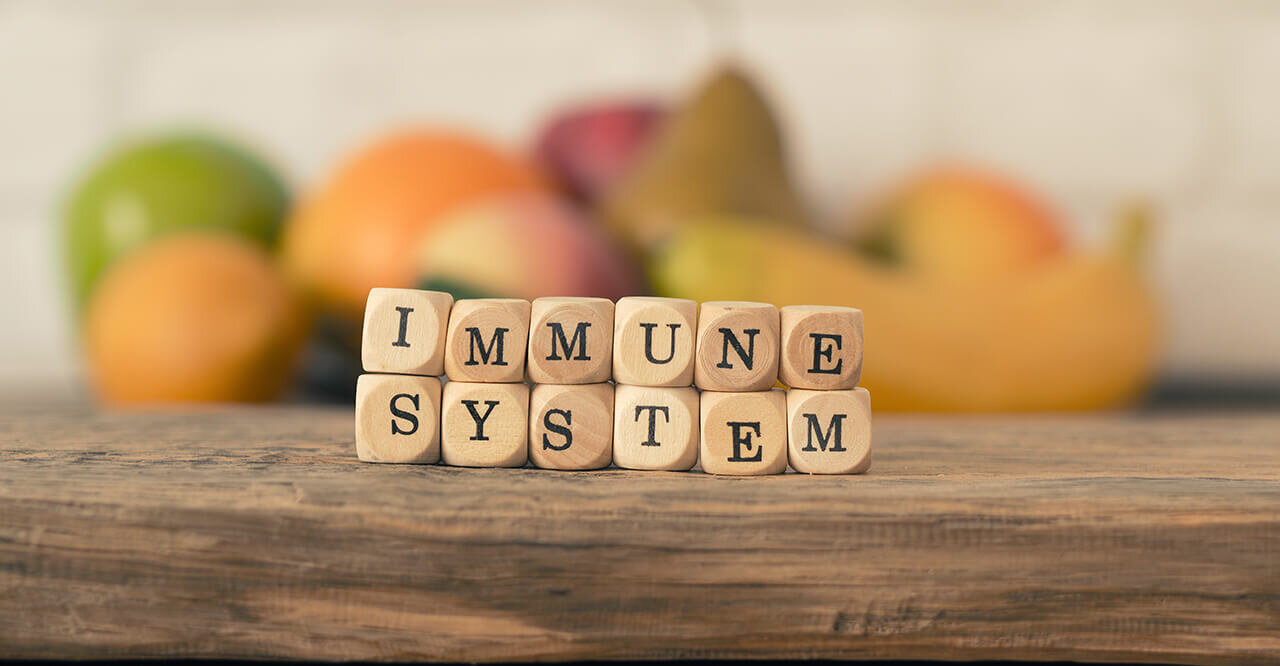食物繊維で健康な体作り
「食物繊維は便秘予防に良い!」
このことは健康の常識としてすでに広く浸透しています。しかし、その割には日本人の食物繊維の摂取量は少ないのが現実です。厚生労働省の調査では、1950年頃に比べて、2010年頃には約半分の食物繊維摂取量まで減少していることが判明しています。
このデータが、糖尿病や高血圧症などの慢性病の増加につながっている可能性は否めないと考えられています。
水溶性食物繊維の働き
食物繊維の中でも水に溶ける性質をもつ「水溶性食物繊維」は、糖尿病・高血圧症、心臓病、脳血管疾患、高コレステロール血症・胆石症などに優れた効能を発揮します。
水溶性食物繊維の最大の特徴は、粘り気を持つゼリー状であること。そのため、胃や腸で溶けた物を包み込んでゆっくり吸収します。糖も同じように時間をかけて吸収されるため、急激な血糖値の上昇やその後の急降下を防ぐことができます。さらにコレステロールや胆汁酸などを吸着して体外に排出する作用や、腸の善玉菌のエサになる点も見逃せません。こうした効果が慢性病予防につながります。
水溶性食物繊維を多く含む食品
干しシイタケ、キクラゲ、昆布、わかめ、干しいちじく、干しプルーン、ジャガイモ、里いも、切り干し大根、ごぼう、ライ麦、オーツ麦、ごま、いんげん豆、ひきわり納豆などに多く含まれています。
特性
粘性
粘着性により胃腸内をゆっくり移動するので、お腹がすきにくく、食べすぎを防ぎます。糖質の吸収をゆるやかにして、食後血糖値の急激な上昇を抑えます。
吸着性
胆汁酸やコレステロールを吸着し、体外に排泄します。
発酵性
大腸内で発酵・分解されると、ビフィズス菌などが増えて腸内環境がよくなり、整腸効果があります。
食物繊維を一日20グラム摂る
戦後の1950年頃、日本人は平均して1日に約24gの食物繊維を摂っていました。
しかしその後、摂取量が減り、2010年頃には平均摂取量は約14gとなり、50年間で約10g減少しています。

では、どうして食物繊維の摂取量が減ってしまったのか?
その理由のひとつとして、食生活の変化が挙げられます。
食生活の欧米化により、肉や乳製品の摂取が増え、食物繊維の摂取量は減少しています。雑穀や玄米ではなく精米されたお米を食べるようになったことも食物繊維の摂取量が減った理由だと考えられています。
不足しがちな食物繊維を摂取するには、日常の食生活において食べる機会が多い、穀類、芋類、豆類、野菜類、果実類、海藻類などが供拾源としてお勧めです。
主食である穀物を食事できちんととり、野菜や芋、海藻などをとり混ぜて食べるには、和食が良いでしょう。豆類や芋類、海藻類にもあうため、食事全体の栄養バランスもよくなります。