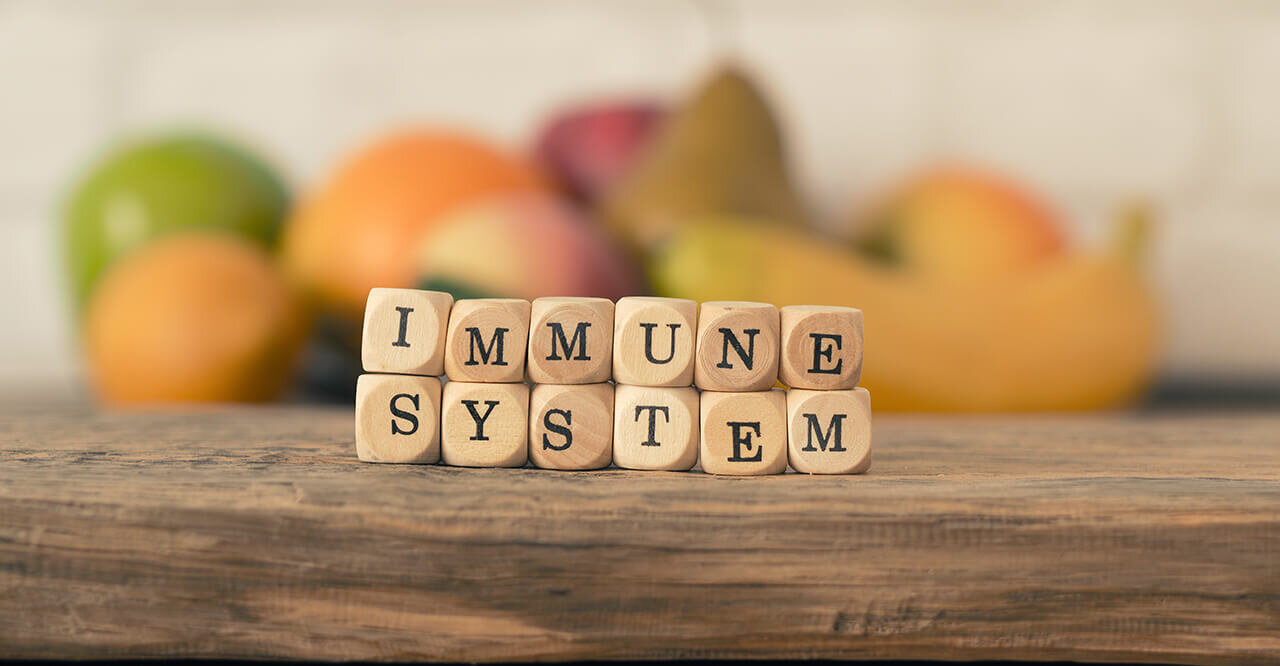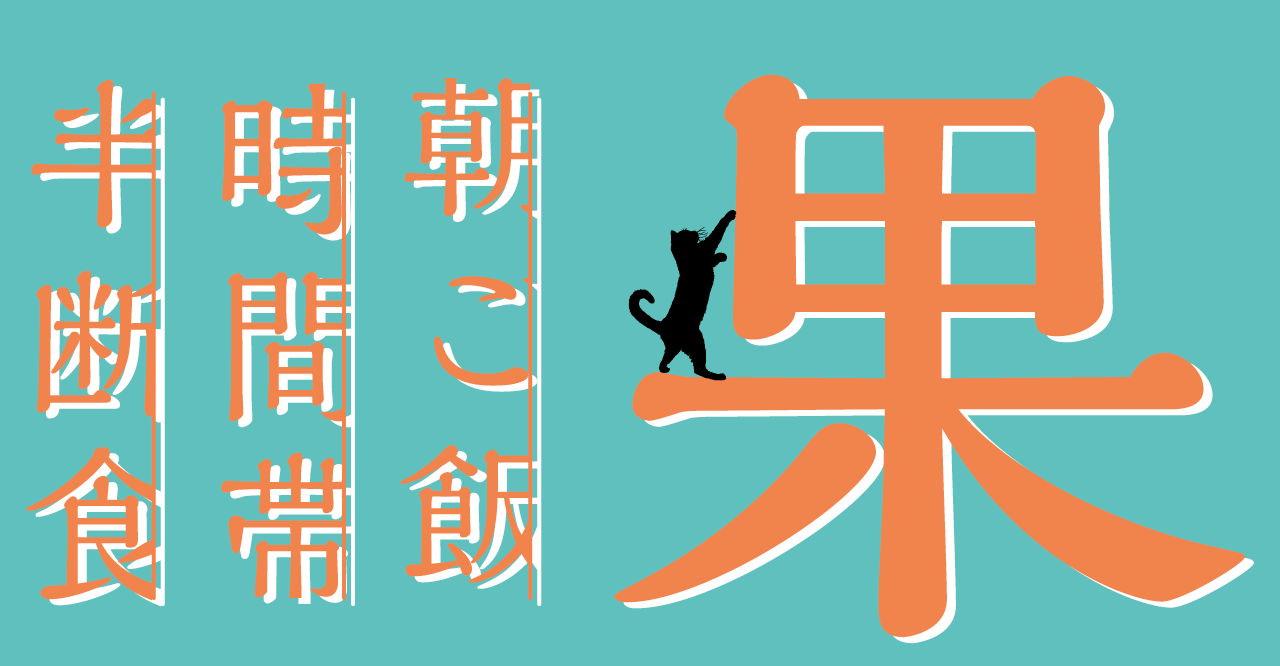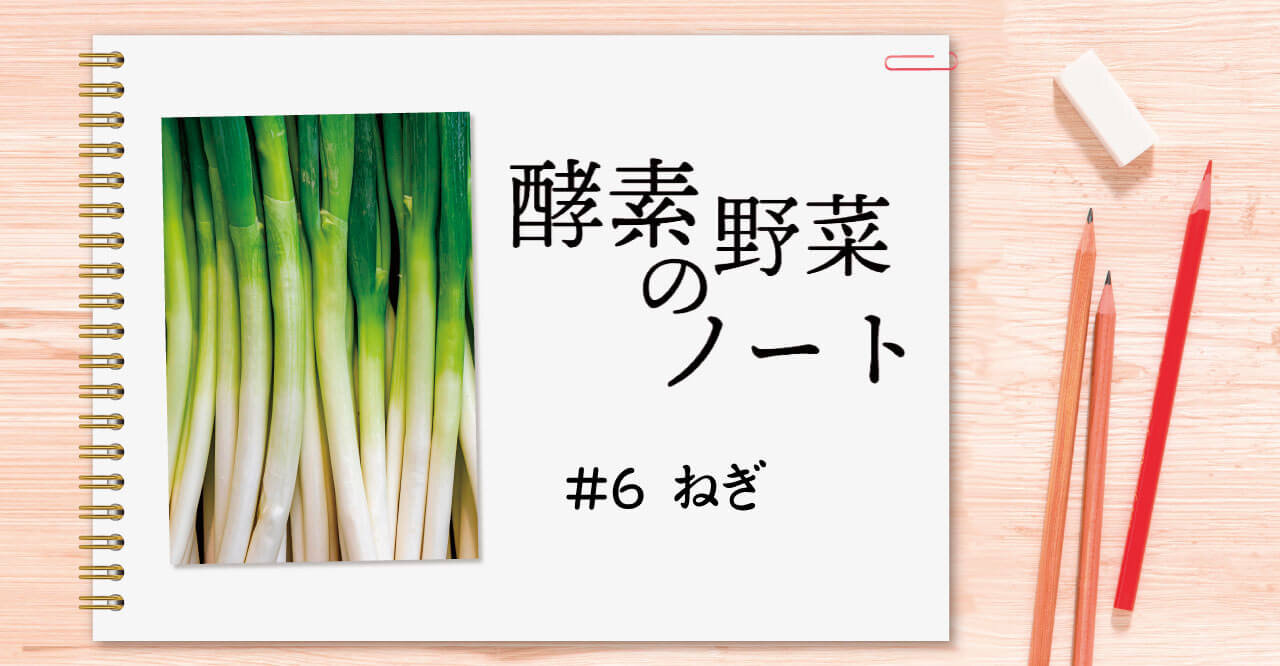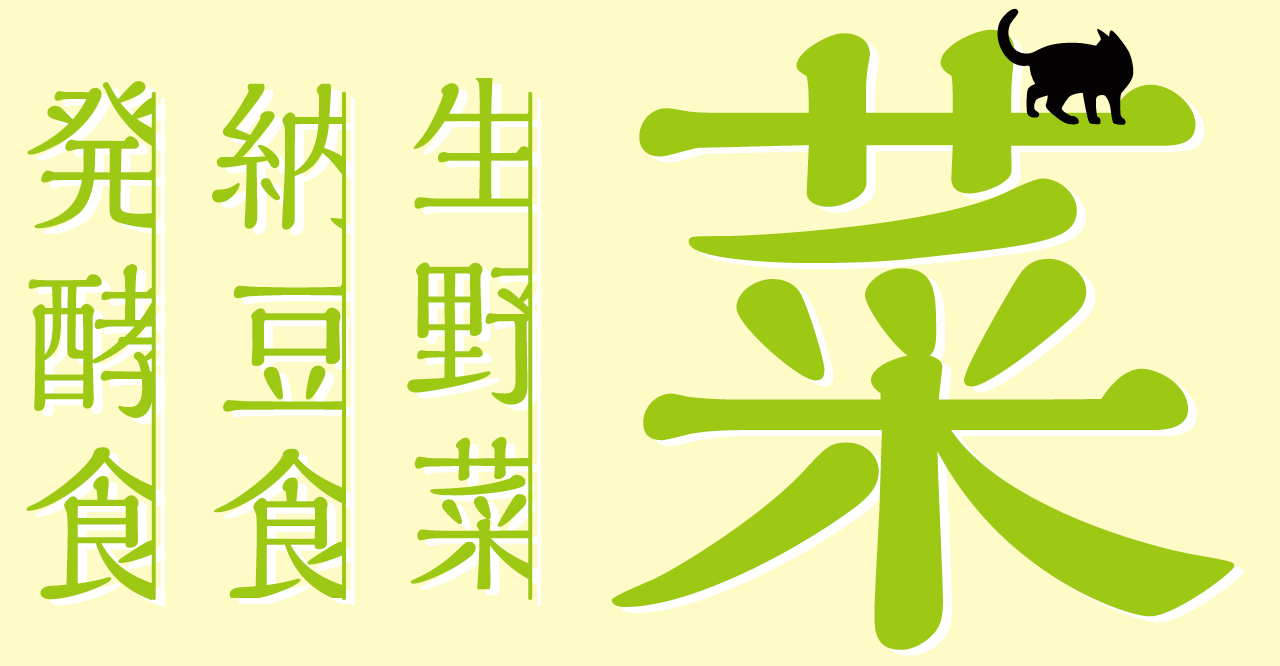免疫力を高める栄養素・栄養成分
健康を維持するのに欠かせない免疫力。
最近では腸活やプチ断食、ビーガンなど、様々な方法で健康を維持しようとされる方が増えてきています。
そんな健康意識の高い方に、免疫力を高める栄養素・栄養成分を摂って、より健康的になっていただければと思います。
ウイルスを撃退するキラーT細胞をつくる
あじやさば、いわしなどの青背の魚がおすすめ
免疫システムを担っているのは、マクロファージや顆粒球、リンパ球などのメンバーからなる"白血球"チームです。 そのリンパ球のひとつ、キラーT細胞は、侵入した異物(主にウイルス)を撃退する最も重要な細胞です。このキラーT細胞は、私たちが良質のタンパク質をとることで体内に大量につくることができます。
良質のタンパク源として、まず挙げられるのが魚や肉。魚のなかで良質のタンパク源としておすすめなのは、あじやさば、いわしなど青背の魚です。青背の魚には、血圧を下げて脳の機能を高めるDHA(ドコサヘキサエン酸)や、血管を拡張して血行をよくするEPA(エイコサペンタエン酸)という不飽和脂肪酸が含まれているからです。

ただし、魚のDHAやEPAは煮る、焼くなどの加熱調理をすると、溶け出したり、酸化しやすくなったりします。そのため、免疫力を高めるためには、有効成分が失われることのない「生」で食べることがベスト。つまり、刺し身、またはサラダや酢の物にすることがおすすめです。
煮魚にした場合は汁に栄養素が溶け出しているので、塩分を控えて調理し、煮汁も一緒にとるようにしましょう。
肉類にも良質のタンパク質が豊富
一方、肉類のタンパク質はすべて良質です。ミネラルでは比較的、鉄が多く含まれ、肉類のなかでも牛肉に多く含まれます。ビタミンAは鶏肉に含まれ、ビタミンB1は豚肉に多く、ビタミンB2は肉類全般に含まれます。
このように、肉類は栄養的にたいへん優れた食品です。ただ、部位によっては脂肪が多いので、食べすぎに気をつけましょう。肉料理を食べるときは野菜を多めにとって肉の摂取量をやや減らすのが賢い食べ方です。
サラダなどつけ合わせには 不足がちなn-3系の油を使用
ところで、油脂類は、含まれる脂肪酸(油脂の成分のこと)の種類によって、性質や働きが違うのをご存じでしょうか。 脂肪酸には、現在わかっているだけでも数多くの種類がありますが、大きく2つに分けられます。
飽和脂肪酸
肉類やバターなど、動物性の脂肪に多く含まれます。必要に応じて体内でつくることができます。ときどき肉料理を食べれば、不足することはありません。とりすぎると悪玉コレステロールや中性脂肪を増やし、動脈硬化のリスクを高めます。
不飽和脂肪酸
魚介や植物性の油に多く含まれ、コレステロールを下げる働きがあります。不飽和脂肪酸はさらに一価不飽和脂肪酸(n-9系)と多価不飽和脂肪酸(n-6系、n-3系)に分かれ、一価不飽和脂肪酸にはオレイン酸があります。多価不飽和脂肪酸のn-6系には リノール酸が、n-3系にはα-リノレン酸、アラキドン酸、DHA、EPAがあります。
人体内で合成できない多価不飽和脂肪酸は、必須脂肪酸とも呼ばれ、食べ物からとる必要があります。
特に不足しがちなのがn-3系です。n-3系は、青背の魚のほか、えごま油やしそ油などに含まれます。加熱調理をすると酸化されやすいため、サラダなどに生で使うようにします。
それぞれの脂肪酸の性質には一長一短 があるため、これらの脂肪酸はバランスよくとることが大切です。
わかりやすく簡単にいえば、動物性脂肪はとりすぎないようにし、青背の魚を心がけて食べ、植物性油脂は不足しないように注意して食べる、といったことになります。

多くの栄養素が互いに助け合う
ビタミンとミネラルは協力し合って免疫力をアップ
免疫細胞である白血球は、主にタンパク質や脂質、ミネラルからつくられます。免疫機能を調整したり、免疫細胞を活性化する役割は主にビタミンが担当していますが、ビタミンが十分に働くためには、タンパク質やミネラルの協力が必要です。
このように、免疫システムが正常に働くために、多くの栄養素が互いに協力し助け合っています。
ビタミンA
油脂に溶けやすい性質(脂溶性)をもつビタミンです。主に動物性食品に含まれるレチノールと、植物性食品に含まれるカロテンがあります。カロテンは、天然色素であるカロテノイドの一種でプロビタミンAと呼ばれ、体内に入ってから必要な量だけビタミンAに変換されます。
ビタミンAに変わるカロテノイドの種類は数多くありますが、なかでも食品に最も多く含まれ、効率的に変換されるのがβ‐カロテンです。このβ‐カロテンは皮膚や粘膜を強化するだけでなく、白血球のマクロファージの増殖を促進したり、T細胞の働きを高める作用があります。
レバー、うなぎ、あしたば、かぶの葉、カボチャ、小松菜、青じそ、春菊、にんじん、ほうれんそう、モロヘイヤ、すいか、マンゴー etc
ビタミンE
脂溶性のビタミンです。T細胞などの免疫細胞を直接活性化するとともに、免疫抑制物質ができないようにする働きがあります。また、強い抗酸化力で活性酸素による細胞の破壊を防ぎます。
赤ピーマン、かぼちゃ、菜の花、にら、ブロッコリー、アーモンド、アボカド、さんま、めかじき、ぶり、銀だら、サフラワー油 etc
※ビタミンAやEなどの脂溶性ビタミンは、油と一緒にとると体内への吸収力が高まる。炒めるほか、ドレッシングをかけたサラダなどにするとよい。

ビタミンC
水に溶ける性質(水溶性)をもつビタミンです。体内で利用されて余った分は尿と一緒に排泄されます。強力な抗酸化作用、抗ストレス作用があります。ストレスは免疫力を低下させる大きな要因です。また、ビタミンCは白血球の働きを強化します。
赤ピーマン、芽キャベツ、黄ピーマン、菜の花、ブロッコリー、キャベツ、 柿、キウイ、いちご、みかん、オレンジ、グレープフルーツ、パパイア etc
※水溶性ビタミンは、洗ったり、刻んだり、加熱調理をすると損失しやすい弱点がある。生で食べるか、炒めたり、蒸したりする調理法がおすすめ。
亜鉛、セレン
いずれもミネラルの一種です。活性酸素を消す働きをもつ酵素の構成成分で、白血球を活性酸素の害から守ります。また、殺菌作用や抗ウイルス作用もあり、体内に侵入した異物を直接排除して、感染を防ぐ働きもあります。
亜鉛:牡蛎、大豆、レバー、うなぎの蒲焼き、ほたて貝 etc
セレン:うなぎの蒲焼き、サクラエビ、かつお(生)、長ねぎ etc